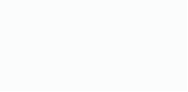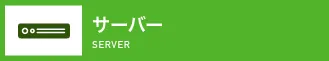建物や都市の新たな可能性を 見いだす研究を AIワークステーションが後押しする
大阪大学様
環境デザインに先進のICTを掛け合わせ、社会が抱えるさまざま課題の解決や新たな付加価値の創造に挑んでいる大阪大学の福田知弘教授。そのための研究やシステム開発を縁の下で支えているのが「AIワークステーション」
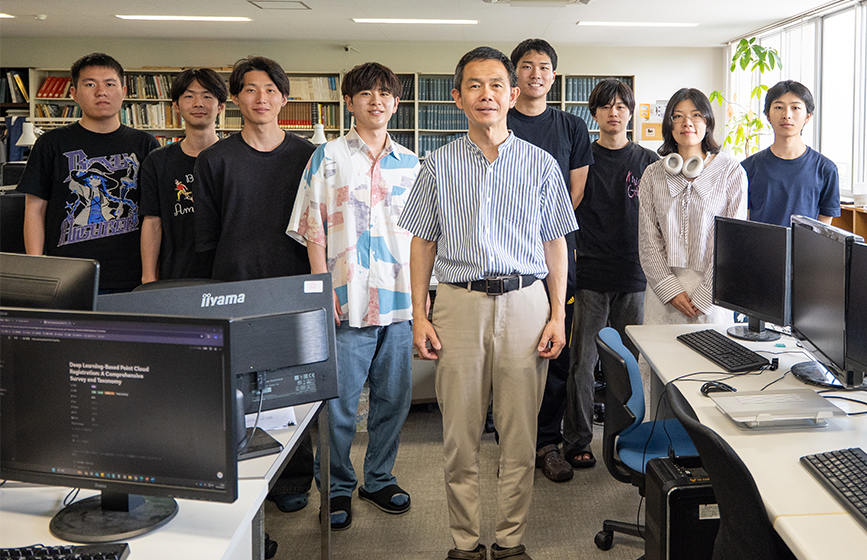
1931年に国内第6番目の帝国大学「大阪帝国大学」として創設された大阪大学。現在は11学部、15研究科、6附置研究所を擁する日本屈指の研究型総合大学である。
また歴史をさかのぼると、その源流は1838年に緒方洪庵が開いた蘭学塾「適塾」にあることから、緒方洪庵の「人のため、世のため、道のため」という教えや適塾の自由闊達な精神、学問的気風をいまに継承。それらを基盤としつつ、大学の理念である「地域に生き世界に伸びる」の下で、教育や研究、さらには社会貢献に日々取り組み続けている。

ビルの解体撤去後の景観をリアルタイムに再現するシステムのイメージ
この大阪大学において、大学院工学研究科 環境エネルギー工学専攻 共生環境デザイン学講座の福田知弘教授は「環境設計情報学領域」を専門分野としている。あまり聞きなれない名称だが、環境設計情報学領域ではまず、建築や土木、都市など人間が作り出した「建造環境(built environment)」に対して、人間・人工物・自然といった要素の関係性を総合的に設計する環境デザインの方法論を構築。さらに、情報通信技術(ICT)を高度活用し、課題解決や新たな付加価値の創造などを可能にする環境デザインシステムを開発している。また、環境・土木・建築・都市工学におけるICT関連の研究として、特にAIやデジタルツイン、拡張・複合現実とバーチャルリアリティ(AR/MR/VR)、3次元計測とプロダクトモデルなどの技術に関する研究ならびに、それらを共生環境デザインに応用する研究にも対応。これらによりSociety 5.0、すなわち「超スマート社会」の実現を目指している。
「この分野の研究としては、例えば以前だと“CGを使った都市の可視化”などがありました。しかし近年は、VRやリアルタイムレンダリングによる現実世界とCGの合成(MR/AR)が増えています。また、これらに取り組むうえで私は『コンピュータがいかに現実の世界を理解するか』が非常に大切だと考えています。なぜなら、そこまでに至らないとせっかくの研究が“現実世界とCGの単なる重ね合わせ”で終わってしまうからです」(福田教授)
VR/ARや生成AIを活用多彩な研究・開発に挑む

大阪大学 大学院工学研究科 環境エネルギー工学専攻 共生環境デザイン学講座 環境設計情報学領域 教授 博士(工学) 福田知弘氏
アナログ的な要素が強い建造環境と最新のデジタル技術を掛け合わせている福田教授の研究・開発は、その“多彩さ”も特徴の1つとなる。例えば長年手掛けている研究の1つに、建物を検出するセマンティックセグメンテーションと建物除去領域のインペインティングを担うGAN(Generativeadversarial network:敵対的生成ネットワーク)を組み合わせ、タブレット端末で撮影した映像から建物を検出し、その部分を違和感なく空の景色に置き換えるシステムの開発がある。このシステムを使えば「ビルの解体撤去後の景観をMR/DR(複合現実/隠消現実)でリアルタイムに確認する」といったことが可能になる。
また災害関連の取り組みとしては、デジタルツインなどを活用して洪水のシミュレーション結果を実際の場所でリアルタイムにMRで確認・検討できる仕組みなどを開発。そのほか、3D Gaussian Splattingによる点群の再構成を用いた屋内空間のサーフェスモデリング法、VRによる安土城の高精度表現、水木しげるロードのリニューアルにおけるVRでのSfM(Structure from Motion)によるブロンズ像作成なども手掛けているそうだが、研究内容のバリエーションに加えて、そこで使われている技術の多彩さも見逃せないポイントだ。
このように、福田教授はVR/ARや生成AIなどのさまざまな最新技術を研究に利活用しているわけだが、ここで必要不可欠な存在となっているのが、膨大な量の計算を高速に処理できる「GPU」である。福田教授によれば、GPUをデータ解析などに利用し始めたのは2015年ごろから。最初のころの取り組みとしては、「ディープラーニングで風景の写真データから“空”の領域を検出する研究」がある。
また、その研究で使用したPCは学生を含めた自分たちでパーツを購入して自作。このやり方はいまも主流となっており「直近で購入した高性能なGPUも自作PCで運用しています」とのことだ。
ワークステーションの導入と学生の育成はバランスが大切
しかし、自作PCにまったく問題がないわけでもない。例えば、自作PCではGPUが持つ100%の性能を発揮できないケースがあるほか、動作の安定性にも少なからず不安があったという。そこで福田教授は近年、1ランク上の環境構築と研究成果のクオリティアップを目的に、高性能GPUを搭載する既成のAIワークステーションも活用している。
「VR/ARや生成AIなどを活用した研究において、複数タスクの並行作業を途中で失敗することなくスムーズに処理できるような“PCの安定性”は、意外とあなどれません。安定性が向上すれば作業効率が上がって研究もはかどりますし、納期や品質の要求レベルが高い行政や企業との共同研究に対しても安心感が高まるからです」(福田教授)
そのほか、例えば自作PCでは「学生が選んださまざまな設定やチューニングが必ずしもベストとは限らない」という課題もあるそうだが、プロのエンジニアがチューニングした既成のAIワークステーションが「自作マシンのベンチマークになるのではないか」と福田教授は考える。また、学生には「サポート対応で研究室に来訪したプロのエンジニアの作業などを見るように」とアドバイス。プロの手際の良さや使っている道具を見るだけでもPCを自作する際の参考になることから、その意味では「学生には、こういったチャンスを自身のスキルアップに役立てて欲しい」と笑みを見せた。
一方で、AIワークステーションの導入によって、これまでに学生が自作PCにかけてきた手間や時間を削減できたとしても、福田教授はそれを手放しで喜ぶわけではない。なぜなら、福田教授は「自分が使っているツールについて知ることも研究の一部。すべて業者任せでは本当の研究にはならない」と考えているから。そのバランスをどう取るかが「難しいところです」と教育者ならではの悩みも語った。
いまは不可能でも最新技術が研究の可能性をさらに広げる

旧緒方洪庵住宅の点群データ(左)と、取得データから作成された3Dモデル(右)のイメージ。大阪大学適塾記念センター 提供。3DモデルはWebページ(https://sketchfab.com/Tekijuku_UOsaka/models)で公開中
今後も、さまざまな挑戦を続けていく福田教授。その研究・開発を加速させるためには、さらなる作業効率の向上や新しい技術の導入などが欠かせない。
例えば2023年には、適塾の建物で国の重要文化財に指定されている「旧緒方洪庵住宅」に関するクラウドファンディングを行い、保全活動の一環として「3D写真記録(フォトグラメトリ)」と「点群データ調査(3Dスキャン)」を実施。福田教授も取得データの確認などで参画し、今後不測の事態で破損・消失しても「復興に十分役立てられる精緻な点群データを取得できた」と振り返る一方で、現状のPC環境では最高精度の点群データをレンダリングできず「データ量を減らしてミドルレベルの精度で対応しました」との課題も吐露する。
また、現在は「洪水前後の2枚の写真からAI解析で浸水領域を判定するシステム」の開発にも着手しているが、GPUを使ったAI解析には3~4日の時間を要するとのこと。開発を加速させるためには、AI解析のさらなるスピードアップが重要となる。
そのほか、福田研究室では最新の取り組みとして、生成AIやGNN(Graph Neural Networks)を組み合わせた「建築におけるフロアプランの自動作成システム」を研究中だ。このシステムが実現されると、例えば建物のアウトラインが決まっている場合、「要望に応じた部屋の構成や間取り、家具のレイアウトなどを自動的に作成して提案してくれる」ほか、建築家以外の素人が考えた「設計図やプランの点検・解析も可能になる」という。
「いまは不可能、あるいは人力でなければできないことであっても、AIなどの最新技術を活用することで“可能性を広げられる”という点はとても重要です。もちろん、既存の課題を解決することは重要ですが、“新しい何かを具現化していく”ことも非常に大切だと感じています」(福田教授)
大阪大学様の使用モデル